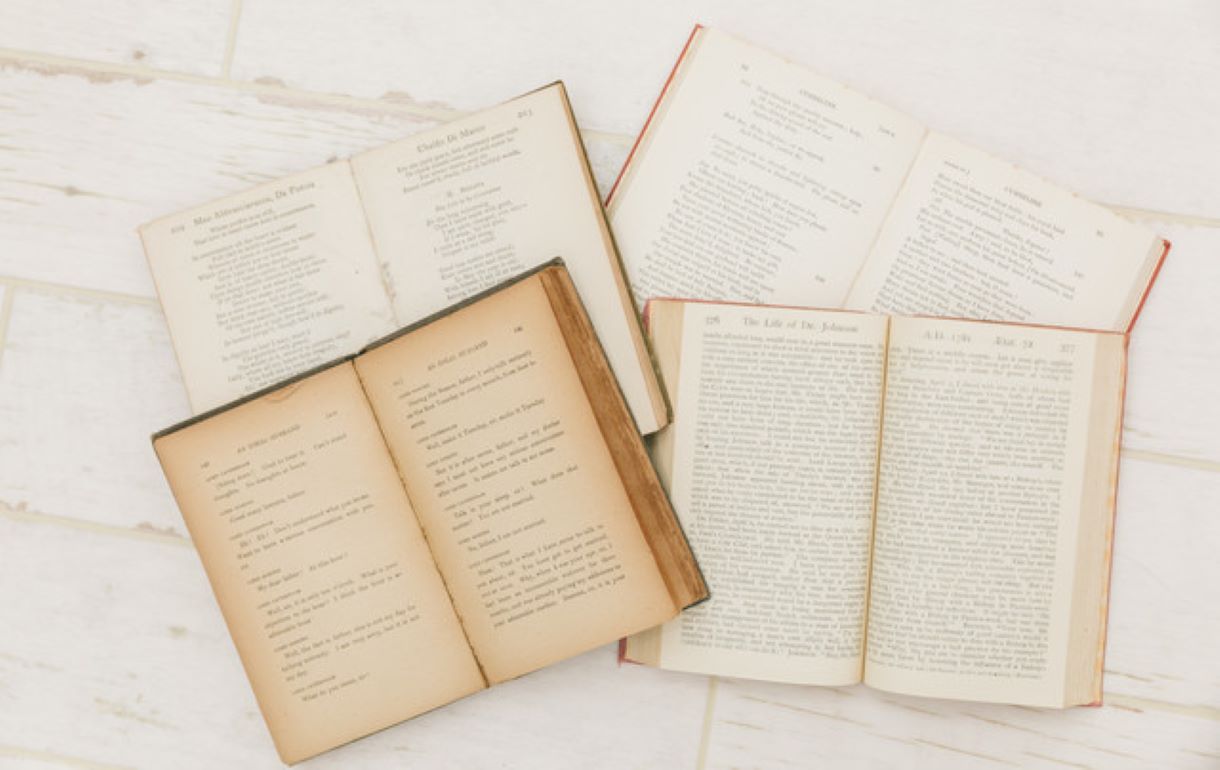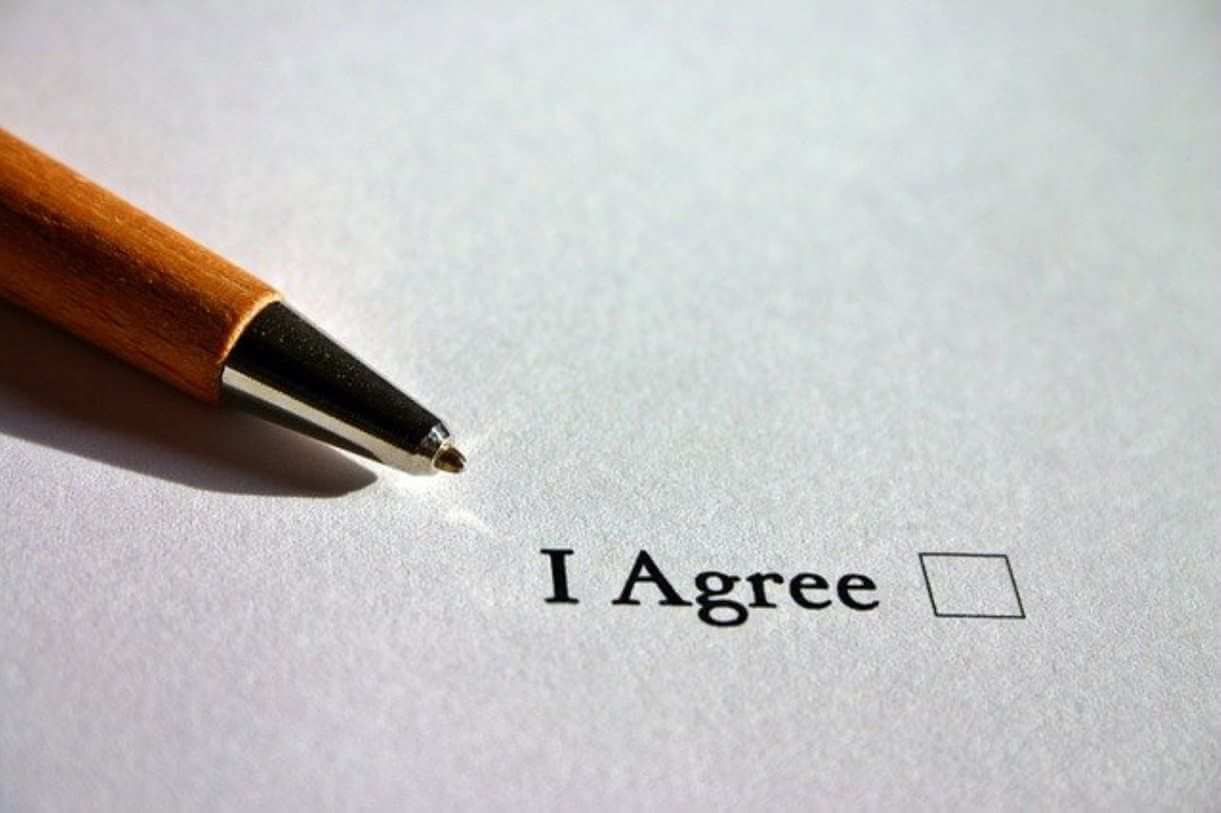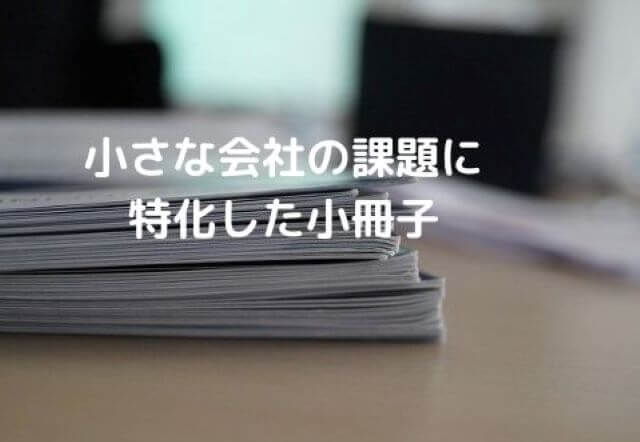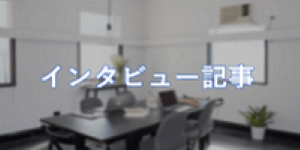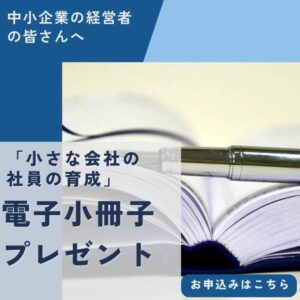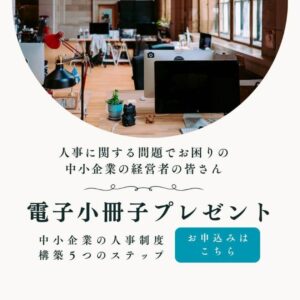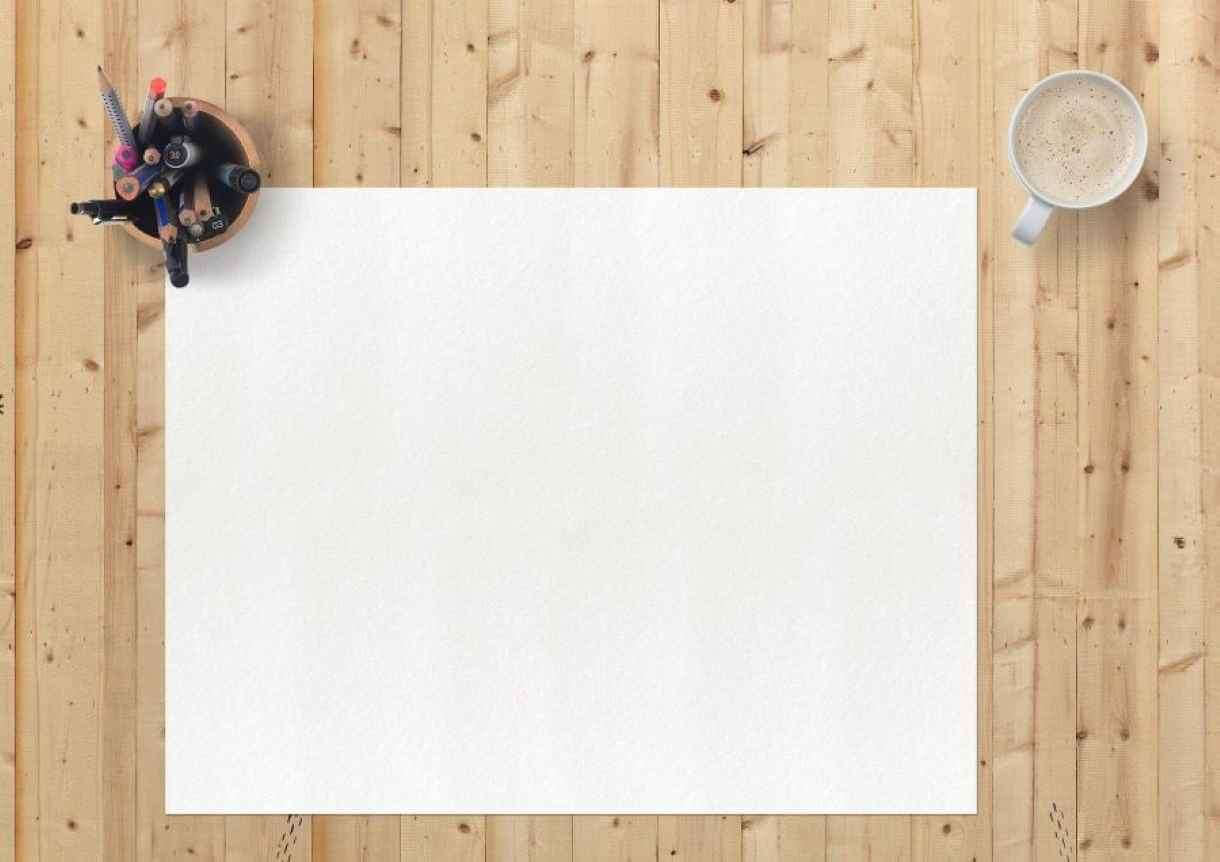
最近では、セクハラという言葉だけでなく、パワハラという言葉も一般的になっております。
各企業で研修を開催するなど、パワハラに対する対応を取るようになっております。
したがって、社員の人たちにもだいぶ認識されるようになってきたようです。
それでも、パワハラによる被害は、相変わらず存在し後を絶ちません。
パワハラとは
一方で、セクハラについても、だいぶ前から世間でも広がり、
各企業では研修を実施したりして、それなりに社員の間にも浸透しているようです。
企業がセクハラ対策に力を入れ、下火になる一方で、それに代わるようにパワハラが表に出るようになりました。
そこで、各企業では、研修等を行い、社内に浸透するよう努力をしてきました。
にもかかわらず、パワハラはなかなか収まらないようです。研修だけでは、足りないのでしょうか。
パワハラは、近年ではマスコミ等でも取り上げられるようになり、社会一般に知られるようになりました。
このパワハラという言葉は、ご存じの方も多いと思いますが、日本の人が考えた和製英語です。
もともとパワーハラスメントという表現でしたが、それを短縮し、パワハラという言い方をしております。
昔は、パワハラという言葉もなく、現在の事象でいうパワハラは社内のあちこちで生じておりました。
かつては、上司による叱咤激励が激しくなりすぎ、それが原因で退職した人も多いと記憶しています。
今も同じようなケースは多いのかもしれません。昔も今も変わらないのでしょう。
上司としては、かつて自分が受けたように、指導するつもりで、激しくしかりつけるのでしょうけれど、人によって感じ方は違います。
耐えられなくなって会社を辞めてしまう人もおります。
また、パワハラが激しくなると、パワハラを受けた人はうつ病にかかり易くなります。
うつ病になる原因として、長時間残業や人間関係が挙げられます。
社員がうつ病に陥り、長期休業に入ってしまうと、もちろん本人も大変ですが、部署内で残された人たちもたまりません。
パワハラの原因および対応
一方で、パワハラについては、パワハラをする人に焦点を当てるのが一般的ですが、される側もそれなりに問題があるケースもあります。
何度も同じミスを繰り返し、上司もたまりかねて怒鳴ってしまうということもあります。
また、仕事を何度教えても理解できないので、つい怒鳴ってしまうということもあるでしょう。
精神的に落ち込みやすい人などは、少し注意を受けただけでも精神的に打撃を受けたように感じてしまいます。
このようにパワハラは片方だけでなく、もう一方の側に対しても注視していく必要があります。
現場を統括する管理職の立場としては、部下がミスをしたり、仕事が期日までに出来なかったりした場合、
感情に任せて怒鳴りつけるのではなく、まず、その人が抱えている仕事の内容や本人の性格などを理解します。
その上で、根本となる原因を指摘するなどの対処が求められます。
つまり管理職としての立場では、普段から主観的にならずに、客観的な立場で考えるようにすることが大切なのです。
とはいえ、日常業務に忙殺されている管理職はそのような余裕はありません。
問題を起こして部署の足を引っ張らないようにしてほしい、と思っていることでしょう。
ただでさえ忙しいのに問題を起こしたら、更に忙しくなってしまうと考えます。
このように、日頃からカリカリすると、精神的にも余裕がなくなってしまうのです。
さらに部下との相性もあります。日頃からよく思っていないと、余裕がないときに、思わず怒鳴ってしまうのです。(管理職の適切な登用については、弊社ブログ『管理職の登用を適切に行い組織の底上げを図る』をご参照ください。)
こうしたことはよくある光景かもしれません。しかし、会社としてそのままにしておくことはできません。
問題が生じてから対応すると後手に回ってしまいます。
ある程度社員数のある会社であれば、
問題を起こしそうな社員を異動させるとか、集中的に教育するとか、何かしらの方法を取ることはできるでしょう。
しかし、人数も限られ、時間的にもコスト的にも余裕がない中小企業では、そうすることもできません。
そのような場合、会社としても、その部署に余分な仕事を回さないようにします。
管理職の人が、多少余裕ができるのを待ちます。
そして、管理職に対し、部下指導や組織運営などを指導していくのです。
管理職に求められる役割
部署を預かる管理職は、部下の性格や現在行っている仕事の進捗などを理解した上で、仕事を与えていく必要があります。
部下の性格については、日頃から接しているとだいたいわかってくるものです。
また、仕事以外のところで部下と接すると意外な発見をすることもあり、別な面を見ることもできます。
そして、部下の仕事の進捗については、エクセルシートなどを利用し、自分なりの方法を見出し、管理します。
そうすることで、部下が、どれくらい仕事が溜まっているか、あるいは余裕があるかなどわかってきます。
もちろん、そのためには、部署内の業務を事前に理解しておかなければなりません。
これだけでも、余分な軋轢は避けることができます。
そして、パワハラを避け、自分の部下の管理がスムーズに行われるのです。
(管理職の教育については、弊社ブログ『組織が機能するための管理職の教育』をご参照ください。)
まとめ
パワハラは上司が意識しなくても、部下が感じてしまうこともあります。
会社が研修を施すことで、ある程度は避けることができると思います。しかし、根本から解決することにはつながりません。
管理職による、部下に対する業務の管理など、自分なりの方法で業務がスムーズに進むようにします。
そしてパワハラになりそうな雰囲気を作らないようにすることが大切です。