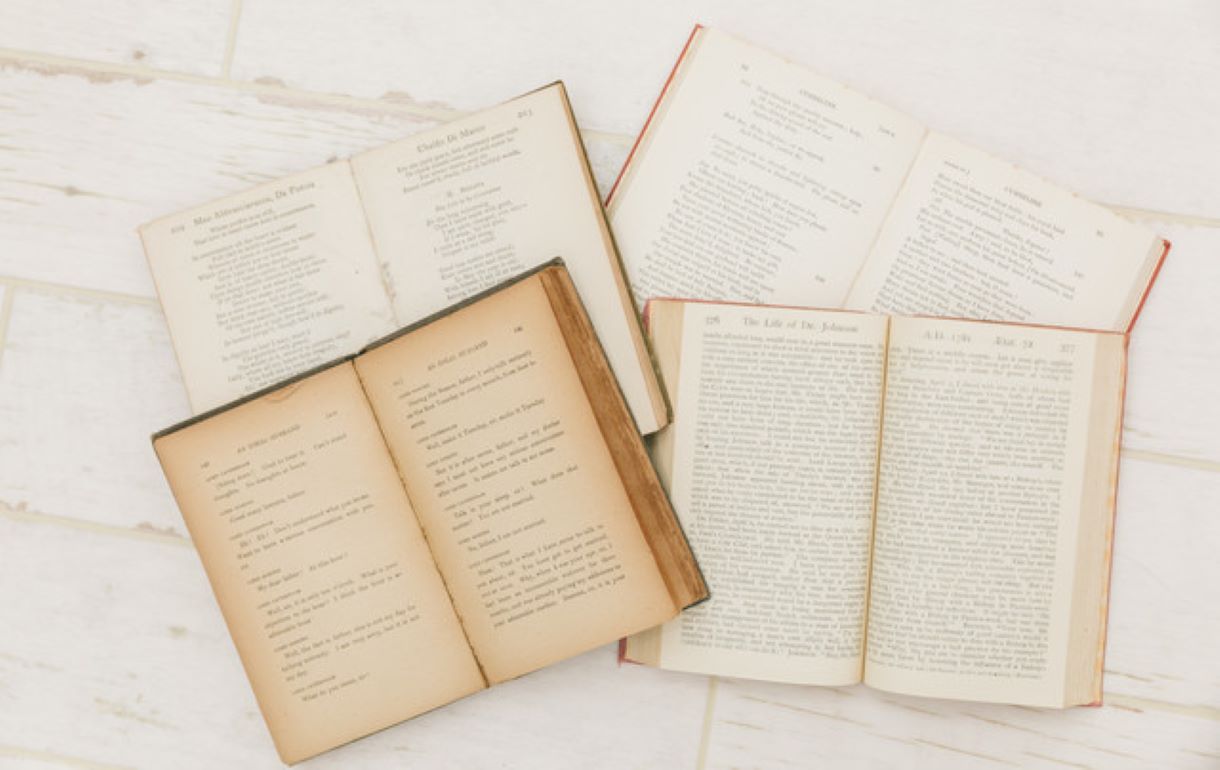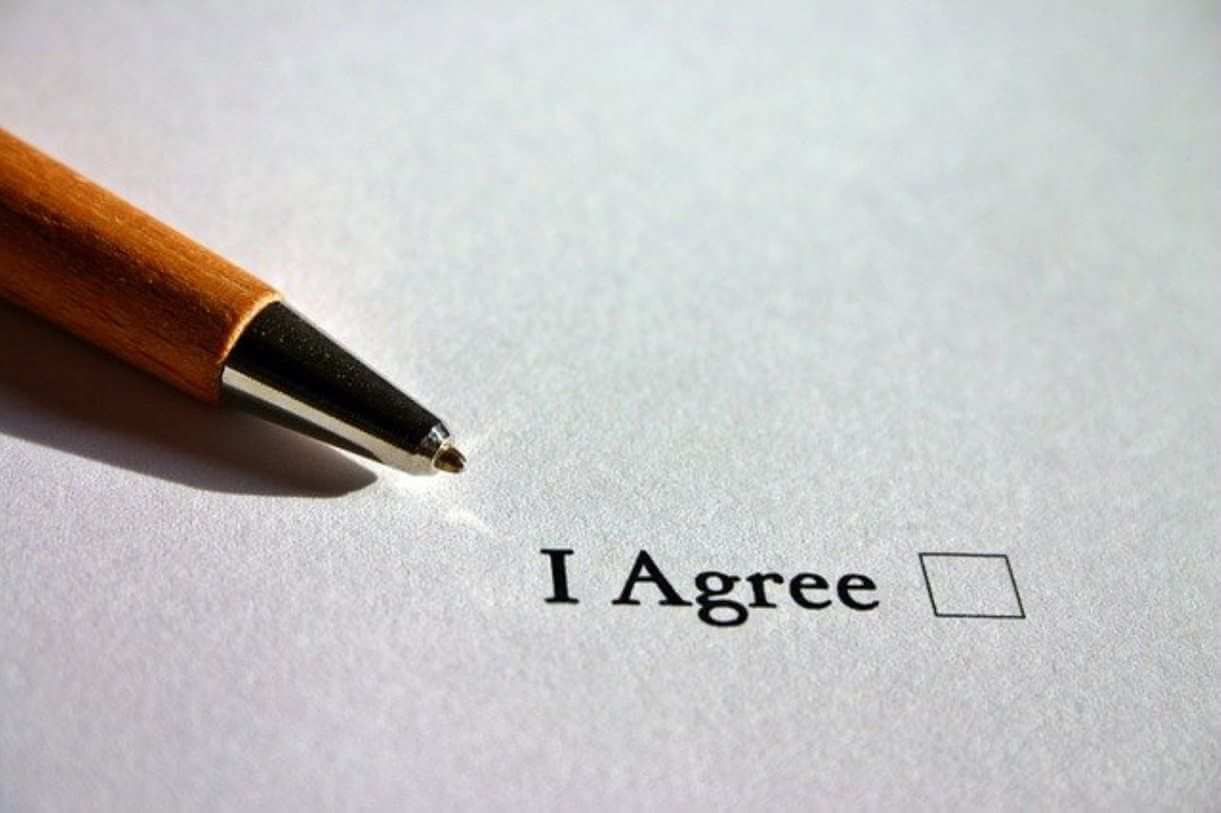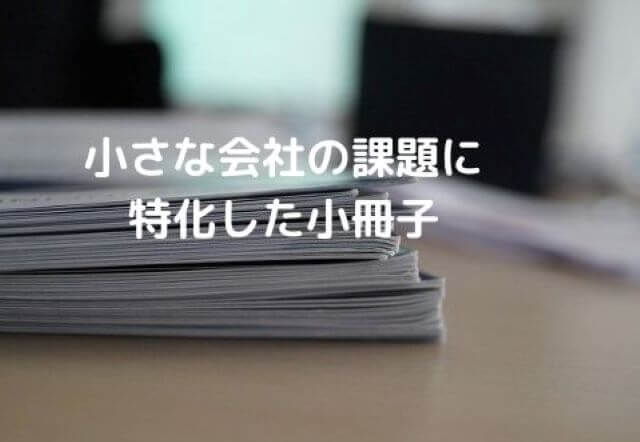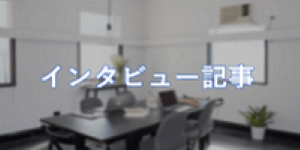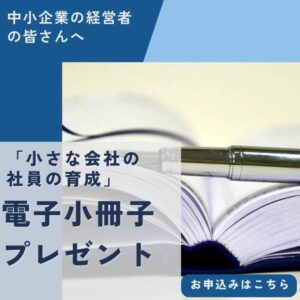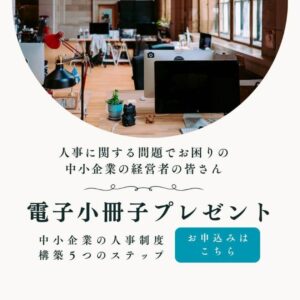これまで日本の企業は、人事考課に基づく評価の仕組みを中心に、人事制度を実践してきました。
管理者が自分の部下に対して、指定された一定の期間に観察し、結果を評価します。
考課要素(規律性、責任性といった、評価するための項目)ごとに点数で評価し、それらを合計することで評価していきます。
実際には人事考課表という表の中でそうしたことが行われます。
人事考課の役割
一般には評語(評価結果をSABCDや12345などいくつかの段階に分けて表すもの)をつけることで部下を評価していきます。
この制度は、ある時代までは、よく機能していました。
評価する側もされる側も理解していましたので、それなりに機能することができました。
現在もこの制度を利用している企業も多いようです。
企業によって多少異なるかもしれませんが、能力考課は主に昇給昇格に、業績評価は賞与に使用されてきました。
現在でもそのような使い方をしている企業も多いと思います。
人事考課表の中の評価項目も職位が上位にいくほど、責任感や協調性といった情意的な評価から実績を評価する項目で評価するようになり、職位に応じて評価の項目も異なってきます。
評価をする側も会社が用意する研修を受け、評価の仕方を学び、できるだけ正しく評価するようにします。
ただし、どうしても評価者によって、多少の評価のくせが生じることもあるようです。
ただ、中には、あまり部下の評価に関心を示さない人もおります。
日々の仕事に目が向き、部下の管理に疎かになる人は少なからずおります。
会社はそのような人に対しても、状況を注視する必要があります。
企業における人事考課の変遷
一方、時代とともに経済も変化し、企業側も社員の増加が望めなくなり、その分既存社員の負担が増え、人事考課の運用も従来に比べ難しくなってきました。
さらに管理者についても、通常業務以外にもエキストラの業務が増え、部下の面倒を見る時間も取れなくなってきました。
そして部下は成長する機会もなく、人によっては将来に漠然と不安を抱え、不平不満をこぼすようになります。
会社の中では次第に現場と経営との間の溝が大きくなってきました。
バブル経済が崩壊した後も、日本社会では、能力主義といいながら年功序列の意識が抜けず、従来的な昇給や昇進続けてきました。
終身雇用の時代であれば、年功序列は機能してきましたが、先が読めない時代になり、会社も時代の流れに合わせ、会社を存続させるため、終身雇用をあきらめるようになりました。
一方で、企業はなかなか昔のやり方を変えることができず、従来の人事考課制度を含めた人事諸制度を継続してきたのです。
このような中で、転職雑誌が売れるようになり、次第に転職が一般化していきます。
企業としても、会社の将来を担う人たちが、適切な評価を受けられないと会社に不満を持ち、退職してしまったのではたまりません。
社員の退職への対応については、『退職防止』のページをご参照ください。
こうした中で成果に基づいて評価しようという考えが出てきて、次第に企業の中に目標管理制度が取り入れられるようになります。
もちろん、従来の人事考課制度をそのまま運用している会社もたくさんあります。
どれがよくてどれがダメというものではありません。会社の必要性に合わせて使用すべきです。
時代や環境に応じた人事考課の運用
人事考課制度も運用をしっかりと整備し、わかりやすいものにすることと、部下の育成をしっかりすることで、充分に運用し続けることができます。
評価結果を正しくフィードバックすることで、納得性は高まるのでしょう。
そして、人事考課上の考課要素一つひとつについて、会社の方向性に合わせて変更していくことにより効果的に運用することができます。
他のことでも同じようなことが言えるのですが、人事考課の中身あるいは使い方も自分たちの使いやすいように変えていくことも必要なのかもしれません。
会社がどのような方向に進み、どのように変えていくのかということについて、社内で十分な議論をして計画を進めます。
そして、その中に人事制度を組み入れ、人事制度そのものがよりよいものにしていくのです。
まとめ
人事考課は昔から日本の企業では利用してきました。
それでも時代とともに変化させないと自分たちの考え方とそぐわないものになってきます。
時代に合わせ、自分たちの利用しやすいように変えていくべきものなのです。