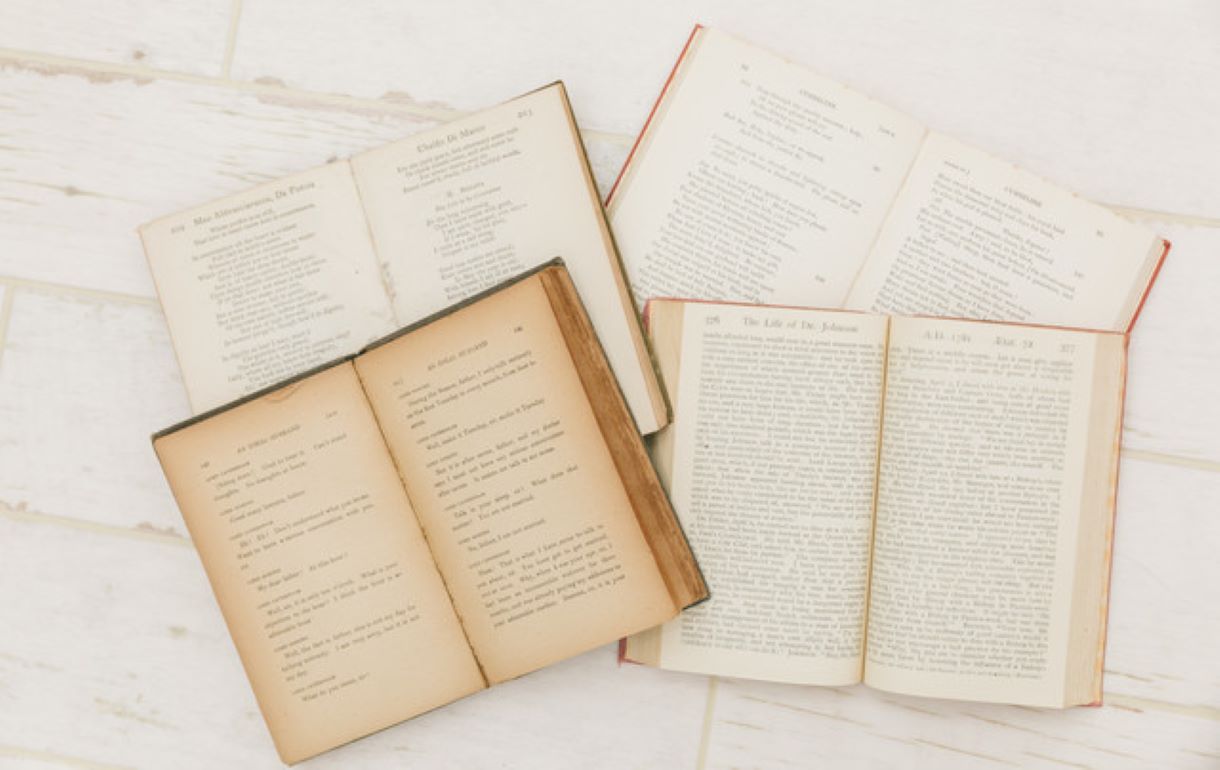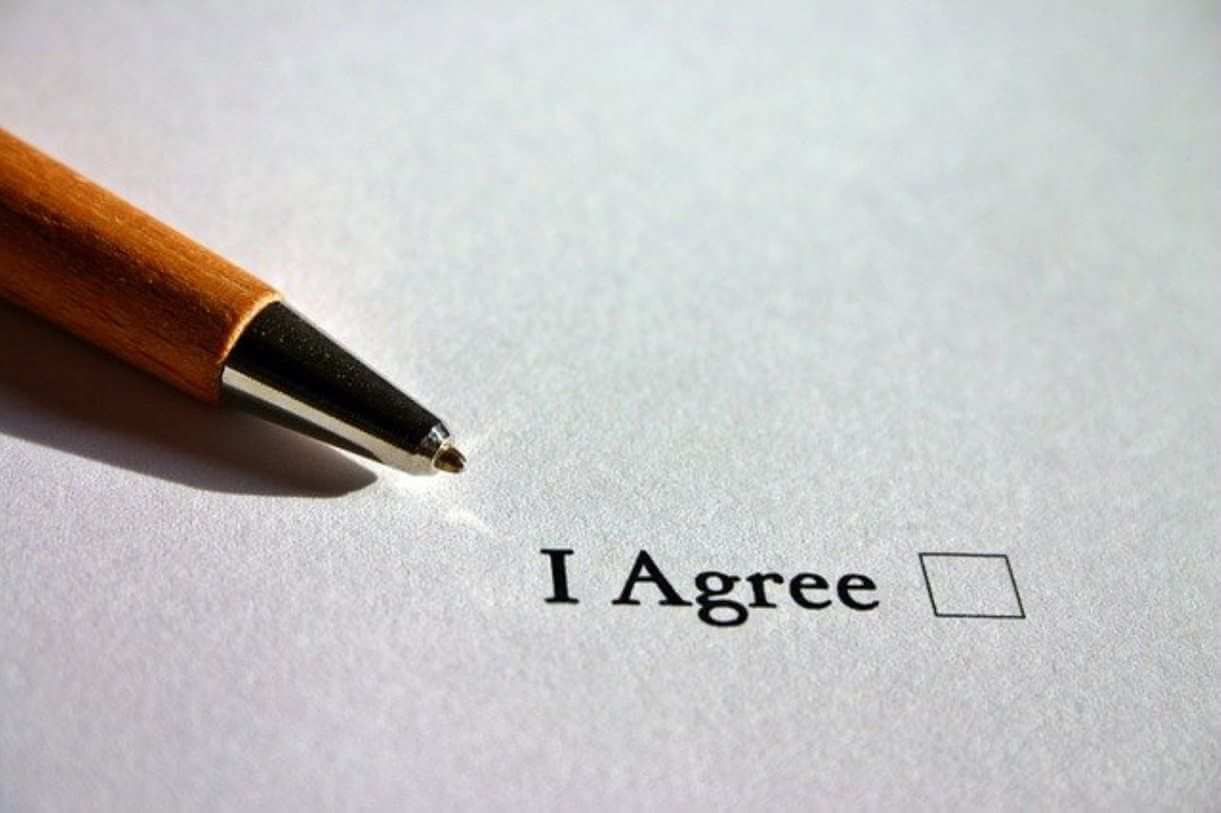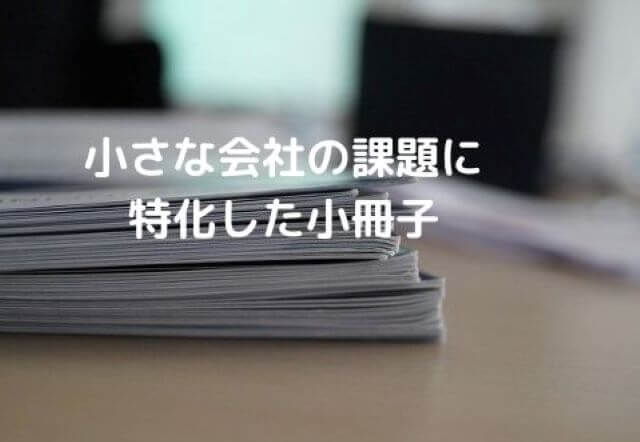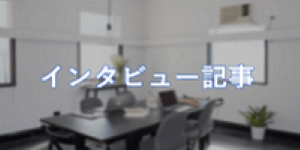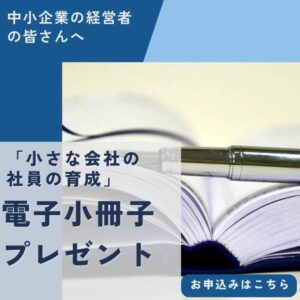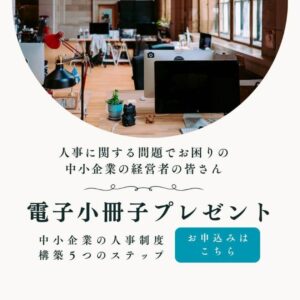労働時間の管理については、すでにだいぶ前からタイムカードのような、客観的に示されるものを使うよう行政の指導がありました。
それ以前は、手書きで出退勤を記入する勤務表というもの(会社によって表現は異なります)を利用している企業が多くありました。
これは社員が自己申告で手書きするものですので、いくらでも出退勤の時間の操作ができるようなものでした。
社員からすると2、3分出社時間が遅くなっても定時に出社したことにすることができます。
また、管理者からすると、自部門の残業を減らすため、残業しても定時に退社したように勤務表に記入するよう、部下に指示することができるのです。
もちろん、そのようなサービス残業は各方面からだいぶ指摘されるようになり、現在ではそのような事例はないと思います。
残業削減の風潮
このように、各社過剰労働の上サービス残業もあり、次第に行政が指導するようになったのです。それでも当時はあまり改善されませんでした。
日本経済が長期にわたる不況ということもあり、行政も景気回復の足を引っ張りたくないという思いもあったかもしれません。
しかしながら、近年行政もサービス残業の撲滅に動くようになり、ご存じのとおり法改正もあって、残業の管理も厳しくなりました。
ところで、労働時間というものですが、中小企業ではあまり分かっていない経営者も多くいるのではないでしょうか。
しかし、休日労働等を含めると、それだけで1冊の本ができるほど、判例や事例が多く、奥の深い分野なのです。
とはいえ、あまり細かく掘り下げても実りがある分野ではないので、どう向き合うかに力を入れた方がよいでしょう。
労使関係をよくして、労働時間管理を行っている会社もあるほどです。
また、残業時間の管理についてですが、管理者が指示を出して、部下が残業を行うというのが大前提です。
しかし実態は、部下の人たちが、就業時間が過ぎてもそのまま居残り残業してしまうとよくあるのではないでしょうか。
そしてその部下の人たちにとって、残業代は生活費ですので、ある一定の時間までは残業をするということになるのです。変な話ですね。
労働時間の管理
管理者がしっかりと部下指導をして、残業の管理もしていれば、このような話はないのでしょう。
しかし、実際には管理者の人たちも、自分の業務を抱えながら部下指導もし、これ以上どうしろというのか、と思っているのが実際のところではないでしょうか。
そして、管理者の人たちも、部下が担当している仕事をそのまま部下にまかせっきりにし、残業はある程度目をつぶるというところなのでしょう。
労働時間に関する管理の強化が叫ばれておりますが、
逆にこの機会に労働時間管理を利用し、業務の効率化に役立てるようにもっていくという考えもあります。
つまり、労働時間を管理するために、社員の人たちの業務を明らかにし、管理するということです。
社員が多く働いている大企業では、しっかりと業務を管理した上で人員を配置していることでしょう。したがって労働時間管理もなされていることでしょう。
しかし、中小企業では、そうはいきません。
新しく入社した人は、前任から引き継いだ仕事を、そのまま前任に教わったとおりにこなしています。
中には前任のやり方を理解した上で、自分のやり方で、業務を進める人もいるでしょう。
しかし、多くの人は、引き継いだ通りに業務を進めます。
したがって、その仕事が部署全体で、さらには会社全体でどのような位置付けになっており、どれほどのウェートがあるのかということがわかりません。
自分の担当業務なので、さぞかし社内で大きな位置付けであろうと思っているかもしれません。
しかし、全体の流れを確認しながら、分析すると、不必要な部分も出てくるかもしれません。
かつては必要であったもので、それも今時点でも必要と思って対応している、ということもあるでしょう。
でも時代と共にいろいろ変わってくるのです。
その担当者もそこに気付けば、だいぶ処理時間も短くなるかもしれません。
あるいは、部署の中である業務を担当している担当者が非効率で、ほかの人に業務が集中してしまう、ということもあるかもしれません。
そしてそのような部署では、忙しい人と暇な人が分かれてしまっているのです。
そして忙しい人から何とかしてほしいと苦情も出るようになります。
ここまで掘り下げていくと実態が分かり、業務を見直すことも容易になります。
このように、会社で号令をかけて、実施すると、意外に業務管理ができ、結果として労働時間管理がスムーズに行われるかもしれません。
業務の効率化については、弊社ブログ『業務の効率化を図り社内体制を強化する』をご参照ください。
まとめ
残業の削減は喫緊の課題です。しかし、努力しても改善されません。
管理者が中心となって、部署内の業務を見直し、そして仕事の仕方について検証します。
そうすることで、仕事が透明化され、労働時間も管理できるようになります。